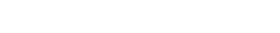辺野古新基地建設事業について 防衛省への質問と回答
辺野古新基地建設事業について
防衛省への質問と回答
みなさまには、日頃より辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議の活動にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
6月3日の辺野古新基地建設に反対する院内集会「沖縄の海と暮らしを守るために」では、沢山の方にご参加いただきました。心よりお礼申し上げます。
民意に反して強行される辺野古新基地建設で、海砂採取海域の海岸の浸食や砂杭による豊かな自然の損失が進んでいる現状について、地元から報告することができました。拡散いただければ幸いです。
さて、当日報告を予定していた防衛省からの回答が、6月の中旬にありました。掲載が遅れましたが、ご活用いただきますようよろしくお願い致します。
尚、質問と解説は、土木技術者の北上田毅さんにご協力いただきました。
7月17日 辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議
事務局長福元勇司
1. 埋立土砂の調達について
1―1. 奄美大島からの土砂・石材調達計画について
沖縄防衛局は昨年8月、沖縄県に対して、「辺野古新基地建設事業において、護岸工事などに使用する石材の調達を担う受注者が、奄美大島からの石材調達を検討している」として、「奄美大島の採石場及び搬出港における特定外来生物の調査を行う」と説明した。
これは、沖縄県の「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」の準備作業だが、その後、特定外来生物の調査は終了したのか?奄美大島の採石場•搬出港で、特定外来生物は確認されたのか、同条例に基づく県への届出書提出は何時になるのか、明らかにされたい。また、調査結果の報告書(最終版がまだの場合、中間的な報告文書)を提出されたい。
奄美大島からは、今も、石材の調達を検討しているだけで、土砂の調達は検討していないのか?
〇 普天間飛行場代替施設建設事業では、石材の調達を担う受注者が、石材の調達先を検討する中で、奄美大島における調査を実施しているところ、当該調査は終了しておらず、沖縄防衛局において、受注者から調査結果を受領していないものと承知している。
〇 また、今後の石材及び埋立土砂の調達先については、現時点で決まっていない。
1―2. 沖縄南部地区からの土砂・石材調達計画について
沖縄南部地区からの埋立土砂採取計画については、沖縄県内、そして全国でも、「戦没者の遺骨が残っている南部地区の土砂を基地建設に使用するな」という強い反対の声が高まっている。
この問題について、岸田首相(当時)は、昨年6月23日の慰霊の日に沖縄戦全戦没者追悼式典に参列した際、「真摯に受け止める」というにとどまっていた従来の首相発言から一歩踏み出し、「(沖縄南部地区では)遺骨収集が進められており、県民が大きな関心を持って注視している。こうした事情も踏まえて調達先を考えなければならない。政府として地元の皆さんの思いはしっかり受け止める」と表明した。
防衛省として、この岸田首相(当時)発言を受け止め、沖縄南部地区の土砂採取計画は撤回すべきではないか?
〇 沖縄県では、先の大戦において県民を巻き込んだ凄惨な地上戦が行われ、軍民合わせて20万人もの尊い生命が失われた。特に本島南部一帯では、多くの住民の方々が犠牲になったものと認識している。
〇 その上で、今後の埋立土砂の調達先については、現時点で決まっていないが、このような歴史のある沖縄において、御遺骨の問題は真摯に受け止める必要があると認識しており、こうしたことを踏まえながら、事業を進めていく考えである。
2. 大浦湾で始まった地盤改良工事について
2―1. 現在までに打設した砂杭本数
本年3月末までに打設した砂杭は、SCP工法で620本、SD工法で700本というが(2025.4.14 NHKTV「辺野古を記録する」)、その後、現在までに打設したそれぞれの砂杭の本数を明らかにされたい。
〇 普天間飛行場代替施設建設事業に係る地盤改良工事の工法ごとの施工本数は、令和7年5月末時点で、サンドコンパクションパイル(SCP)工法が約1,600本、サンドドレーン(SD)工法が約1,200本である。
2-2. 海面下70mまで打設する砂杭本数
ケーソン護岸下部では、サンドコンパクションパイル(SCP)工法で、1万6千本の砂杭を打設するというが、そのうち、海面下70mまで打設する砂杭は何本か?
2-3. 「浮き型工法」の問題点
B27地点付近では軟弱地盤は海面下90mまで続いている。SCP工法では打設する砂杭のうち、「浮き型工法」(砂杭が基礎の支持層に届いていないもの)の砂杭は、何本か?
現地の海底面は傾斜地であるため、「浮き型工法」の場合、砂杭先端部分は下方に拡がるおそれがあるが、砂杭の強度に問題は生じないか?
〇 本事業における地盤改良等の設計は、羽田空港等の多くの海上埋立空港で使用されている、国土交通省が監修した基準に基づいて行われており、海面下最大70mまで砂杭を打設して必要な地盤改良を全て行うことで、構造物等の安定性を十分に確保できるとの結論が得られている。つまり、海面下70mより深いところは地盤改良を行わなくても構造物等の安定性を十分確保できることが確認されている。
〇 その地盤改良の規模については、羽田空港の再拡張事業や関西国際空港の建設事業よりも少ない砂杭等で施工可能なものであり、また、日本企業において、韓国で海面下7
0m、横浜で海面下65mの深さまで施工した実績もあると承知している。
〇 また、その工法についても、羽田空港や関西国際空港、那覇空港でも用いられている、長年にわたり多数の施工実績があるものが採用されている。これらについては、有識者で構成される技術検討会において確認いただいている。
〇 このように、大浦湾側の地盤は、一般的で施工実績が豊富な地盤改良工法により、護岸の安定性を十分に確保することができる強度となり、問題なく埋立地を完成させ、飛行場を建設できるものである。
〇 その上で、本事業において計画しているサンドコンパクションパイル(SCP)工法による施工本数は約1万6千本であるが、打設する砂杭については、海面ではなく、海底面からの杭長で把握しており、お尋ねの各本数についてお答えすることは困難である。
2-4. 作業船の櫓(リーダー)を高くしたことによる安定性喪失
現在、大浦湾には6隻のSCP工法作業船が入っている。工事の特記仕様書では、7
5m級への改造や、船体補強の改造を公費負担で行うとしているが、これらの作業船の櫓(リーダー)を何m高くしたのか、改造に要した総費用はいくらか?
櫓(リーダー)の高さを上げたことにより、台風時等の安定性に支障が生じていないのか?
〇 地盤改良船の櫓(リーダー)は、最大のもので、海面下70mまで貫入するケーシングパイプに対応できる高さのものであると承知しているが、地盤改良船の改造に要した費用についてお答えすることは困難である。
〇 その上で、本事業においては、従来から、気象・海象状況等を踏まえ、安全に留意しながら工事を進めてきたところであり、地盤改良工事についても、安全に留意しながら、着実に作業を進めていくものと承知している。
2―5. チェックボーリングについて
今回の地盤改良工事では、「SCP1000本につき1本程度のチェックボーリング (標準貫入試験)を行う」とされている。SCPは既に1000本以上打設されたと思われるが、チェックボーリングは行われたか?砂杭の強度に問題はなかったか?
〇 現時点において、チェックボーリングは実施していないと承知している。
3. 海砂の使用削減について
辺野古新基地建設事業では、地盤改良工事の敷砂•砂杭、護岸工の中詰材等に、約38
6万㎥もの海砂が使用される。これは沖縄の年間海砂使用量の3〜5年分にもなる膨大な量である。海砂採取は環境への影響が大きく、西日本各地では全面禁止としているところが多い。
防衛省は、「生物多様性国家戦略2023―2030」の閣議決定(2023.3.31)を遵守して、沖縄沿岸部の環境を保護するためにも、辺野古新基地建設事業で使用する海砂の使用削減について検討するべきではないか?
〇 海砂については、砂利採取法に基づき採取計画の認可を受けた事業者が採取を行っており、この認可の手続において、採取場所の環境への配慮も考慮されているものと認識している。
◯ その上で、受注者が、このような手続を経て認可を受けた採取業者から海砂を調達することを、沖縄防衛局において確認することとしている。
4. 大浦湾での土質調査について
防衛省は、昨年8月から、大浦湾の軟弱地盤最深部付近で、「施工管理の一環として地盤改良や埋立による地盤の状況の変化を確認するための土質調査を行っている」ことを認めた。
これは、「動態観測」を実施しているということになるが、「動態観測」は、施工中の沈下及び安定監理を中心としたもので、地盤調査としては各施工ステップでラジオアイソトープコーン貫入試験(RI-CPT)を行うのが通常である。
ところが今回の土質調査は、以前、深場のボーリング試験を実施した際と同タイプの傾動自在型工法の調査船で行われている。以前、県の再三の指示にもかかわらず実施を拒否してきたボーリング試験を実施しているのではないか?
この土質調査の報告書(最終報告書がまだ出されていない場合は、防衛局が指示した調査内容、業者から出された中間報告の文書等)を提出されたい。
〇 沖縄防衛局においては、地盤改良や埋立てによる地盤の状況の変化を確認するため、施工管理の一環として土質調査を行うこととしており、令和6年8月から実施している土質調査では、それに向けて、地盤の状況を把握するため、必要な現地調査を行ったものと承知している。なお、今般の土質調査では、B-27地点において調査を実施していないと承知している。
〇 今般の土質調査については、今後、受注者において、室内試験やその取りまとめ等を行うものと承知しており、現時点において、調査結果を受領していない。
5. 総工事費の見直しについて
辺野古新基地建設事業の総工事費は、設計変更申請書では9300億円とされている。しかし、2006年~2023年度までの総支出額は5319億円、2025年度の
予算額は1918億円(契約ベース)となっている。2024年度の支出額はいくらだったのか、説明されたい。2025年度の予算額を含めると、既に9300億円という総工事費の見積額に達しているのではないか?
中谷防衛大臣は、本年2月5日の衆議院予算委員会で「現時点で総工事費を具体的に見直す段階ではない」と答弁したが、今後、大浦湾での本格工事に入ることから、総工事費の見直しについて、国民に明らかにする時期ではないか?
〇 普天間飛行場代替施設建設事業等に係る経費の状況については、確定した額である支出済額により御説明しているところ、平成18年度から令和5年度までの支出済額の総額は約5,319億円であり、令和6年度の支出済額については、現在、整理中である。
平成18年度:約8億円
平成19年度:約9億円
平成20年度:約45億円
平成21年度:約80億円
平成22年度:約65億円
平成23年度:約14億円
平成24年度:約26億円
平成25年度:約34億円
平成26年度:約203億円
平成27年度:約104億円
平成28年度:約175億円
平成29年度:約507億円
平成30年度:約201億円
令和元年度:約554億円
令和2年度:約547億円
令和3年度:約924億円
令和4年度:約815億円
令和5年度:約1,007億円
〇 普天間飛行場代替施設建設事業等の経費の概略については、令和元年12月、沖縄防衛局が、地盤改良工事の追加に伴う工事計画の見直し結果や、当時の工事の状況等を踏まえ、約9,300億円とお示ししたところである。
〇 公表した当時も御説明しているように、当該経費の概略については、その時点での検討を踏まえたものであり、今後の検訳等によっては変更があり得るものである。
〇 その上で、当該経費の概略については、工事の進捗等を踏まえつつ検討する必要があることから、現時点では具体的に見直す段階にはなく、今後の大浦湾側の工事の進捗等を踏まえて検酎していく。
〇 なお、普天間飛行場代替施設建設事業等における令和6年度予算額は、歳出ベース約1,523億円、契約ベース約1,600億円であり、その内訳は次のとおりである。
(歳出ベース)
・環境影響評価等に要する経費 約45億円
・埋立工事に要する経費のうち、
仮設工事約170億円
護岸工事約410億円
埋立工事約700億円
付帯工事約28億円
・飛行場施設整備に要する経費 約52億円
・キャンプ・シュワブ再編成工事に要する経費 約116億円
・事務費約2億円
(契約ベース)
・環境影響評価等に要する経費約58億円
・埋立工事に要する経費のうち、
仮設工事約71円
護岸工事約405億円
埋立工事約781億円
付帯工事約20億円
・飛行場施設整備に要する経費 約49億円
・キャンプ・シュワブ再編成工事に要する経費 約214億円
・事務費約2億円
〇 普天間飛行場代替施設建設事業等における令和7年度予算額は、歳出ベース約706億円、契約ベース約1,919億円であり、その内訳は次のとおりである。
(歳出ベース)
・環境影響評価等に要する経費 約61億円
・埋立工事に要する経費のうち、
仮設工事約139億円
護岸工事約163億円
埋立工事約197億円
付帯工事約13億円
・飛行場施設整備に要する経費 約24億円
・キャンプ・シュワプ再編成工事に要する経費 約106億円
・事務費約3億円
(契約ベース)
・環境影響評価等に要する経費 約86億円
・埋立工事に要する経昔のうち、
仮設工事約154億円
護岸工事約455億円
埋立工事約846億円
付帯工事約31億円
・飛行場施設整備に要する経費 約45億円
・キャンプ・シュワブ再編成工事に要する経費 約299億円
・事務費約3億円
オール沖縄会議への防衛省回答 解説
1‐1奄美大島からの埋立用材調達問題について
・防衛局は、辺野古埋立のために、奄美大島からの埋立用材(土砂•石材)調達を計画している。沖縄県には、県外からの公有水面埋立用材を調達するには、特定外来生物の侵入を防止するための 「土砂条例」がある。そのため防衛局は、昨秋から奄美大島の採石場・搬出港での特定外来生物の調査を行った。
調査からすでに10ケ月近く経過している。今も「当該調査は終了していない」、「調査結果を受領していない」など、あり得ない。
1‐2. 沖縄南部地区からの土砂調達問題について
・歴代首相は、沖縄南部地区からの土砂調達間題について、「ご遺骨の問題は真摯に受け止める必要がある」というにとどまっていた。しかし岸田首相(当時)は、昨年6月23日の慰霊の日、さらに一 歩進んで、「政府として地元の皆さんの思いはしつかりと受け止める」と明言した。この岸田首相発言を受けて、防衛省としての具体的な対応を明らかにすべきである。
2‐1. 現在までに打設した砂杭本数
・SD 工法の砂杭打設は本年1月29日、SCP工法の打設は2月19日から始まった。5月末時点で、SD工法が約1,200本、SCP工法が約1, 600本打設というが、このペースではSD工法 (総数3万1千本)完了までには8年半、SCP工法(総数1万6千本)完了までには3年を要することになり、計画の遅れは著しい(計画では、 SD工法:約4年、SCP工法:約2年)。
しかも海面下70mまでの地盤改良を行うため、地盤改良作業船は櫓を20mほど高く改造したため、不安定で風に弱い。6月中旬にも台風避難のために地盤改良作業船は大浦湾を離れざるを得なかった。秋までの台風シー ズンは、地盤改良工事はほとんど進まないのではないか。
2‐2. 海面下70 mまで打設する砂杭本数
・今回、防衛省は、「お尋ねの各本数についてお答えすることは困難である」と回答を拒否したが、防衛省は2019年3月、国会議員の質問に対して、「70mまで施工するのは、約2700本」と回答している。
2‐3. 「浮き型工法」の問題点
・地盤改良工事は、羽田空港、関西国際空港等でも行われたが、これらの空港建設個所の海底はなだらかなスロー プの地形であった。しかし、大浦湾は急峻に落ち込んでおり、しかも起伏が多い。SCP工法の砂杭先端は基礎岩盤に到達していないため、砂杭を十分に締め固めることができず、砂杭に所要の強度が確保できない可能性がある。
2‐4. 作業船の櫓(リーダー)を高くしたことによる安定性喪失
・日本では、過去に海面下65mまでの地盤改良を行ったことがあるだけで、海面下70mまでの地盤改良ができる作業船はない。今回、防衛局は公費で、 3隻のSCP作業船の櫓(リーダー)を高くして「75m8級に改造」、3隻を「船体補強の改造」を行った。20 18年の防衛局の報告書では、櫓を高くするには6億円/隻もの費用が必要とされている。公金で改造したのだから、改造費用を明らかにすべきである。
船体の寸法は同じのまま櫓を約20m ほど高くたため、船の重心が高くなり、強風時の安定性に支障が生じている。今回、 6月中旬に地盤改良船が長期間の避難を強いられたのもそのためである。
2‐5.チェックボー リングについて
・サンドコンパクションパイル工法では、砂杭に想定どおりの強度が確保できているかを確認するため、杭芯でのチニックボー リング(標準貫入試験)が必要となる。今回の工事の特記仕様書では、「サンドコンパクションパイル1000本に対して1本程度のチェックボーリングを行うこと」とされている。
すでにサンドコンパクションパイルは約1600本(5月末時点)も打設されているのであるから、「現時点でチェックボーリングは実施していない」というのはあり得ない。
2‐6. 海砂の使用削減について
・海砂採取は、海底の泥を根こそぎポンプで吸い上げ、砂だけをふるい分けた後に、礫・泥等を高濃度の濁水とともに海に戻すという荒っぼい方法で行われるため、自然環境や水産資源、さらに海岸部の浸食•砂浜流出等、深刻な影響を与える。
防衛省は、「砂利採取法に基づき採取計画の認可を受けた事業者から海砂を調達する」というが、「生物多様性国家戦略2023‐2030」の閣議決定を遵守するためにも、海砂の使用削減を目指すべきである。
2‐7. 大浦湾での土質調査について
・辺野古新基地建設事業で沖縄県知事が防衛局の設計変更申請を不承認とした最大の理由は、防衛局が、海面下90mまで軟弱地盤が続いているB27地点で、地盤の強度を直接調べるボーリング試験を行っていないことであった。県は再三にわたり、 B27地点でのボーリング試験を実施するよう求めたが、防衛局は、離れた3地点のボーリング試験結果でB27地点の強度は類推できると主張、B27地点付近でのボーリング試験を頑なに拒否してきた。
しかし防衛局は昨年8月から、大浦湾の軟弱地盤最深部付近でボーリング試験と思われる土質調査を行っている。すでに調査から10ヶ月も経過しており、「現時点で調査結果を受領していない」ことなどありえない。調査結果によっては、設計見直し=再度の設計変更申請が必要となる重要な事態であり、隠ぺいは許されない。